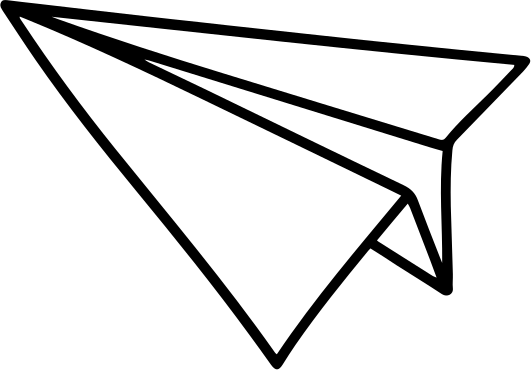 洗濯籠の中に残る「靴下バラバラ事件」の被害者を見ていた俺。犯人の自首は早く「僕のせいかも」って出久が謝ってきた。怒る気にもなれなくて、「左右あってりゃいーよ」って言ったら、「捕まえておかないと再犯するよ」ってむくれながら抱きつかれた。俺がその腰を捕まえると出久は満足そうに笑った。
洗濯籠の中に残る「靴下バラバラ事件」の被害者を見ていた俺。犯人の自首は早く「僕のせいかも」って出久が謝ってきた。怒る気にもなれなくて、「左右あってりゃいーよ」って言ったら、「捕まえておかないと再犯するよ」ってむくれながら抱きつかれた。俺がその腰を捕まえると出久は満足そうに笑った。
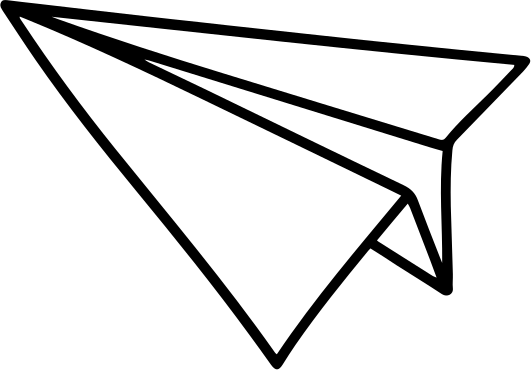 いつの間にか俺の冷蔵庫に曰く『僕セレクト』の調味料が並んでる。スーパー行くたび出久が「これ美味しそう」とか言って籠に入れてくるから、気づけば俺のキッチンは家人以外の好みで染まっている。あいつが選ぶモンは辛さが足りねえが嫌じゃなかった。むしろもっと置いてけ、俺の部屋にお前の気配を。
いつの間にか俺の冷蔵庫に曰く『僕セレクト』の調味料が並んでる。スーパー行くたび出久が「これ美味しそう」とか言って籠に入れてくるから、気づけば俺のキッチンは家人以外の好みで染まっている。あいつが選ぶモンは辛さが足りねえが嫌じゃなかった。むしろもっと置いてけ、俺の部屋にお前の気配を。
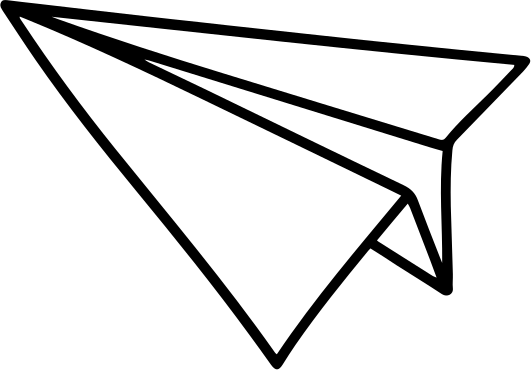 僕の名前を呼ぶ声が今日はやけに低くて甘くて思わず顔を赤くしたら「お前何勝手に照れてんだよ」って笑われた。じゃああれは僕の気のせいだった?って聞いたら君は「違ェけど」って小声で呟いて目を逸らす。じゃあ僕が照れるのも正解だったじゃないかと、僕は耳を赤くする君の背中に抱きついて笑った。
僕の名前を呼ぶ声が今日はやけに低くて甘くて思わず顔を赤くしたら「お前何勝手に照れてんだよ」って笑われた。じゃああれは僕の気のせいだった?って聞いたら君は「違ェけど」って小声で呟いて目を逸らす。じゃあ僕が照れるのも正解だったじゃないかと、僕は耳を赤くする君の背中に抱きついて笑った。
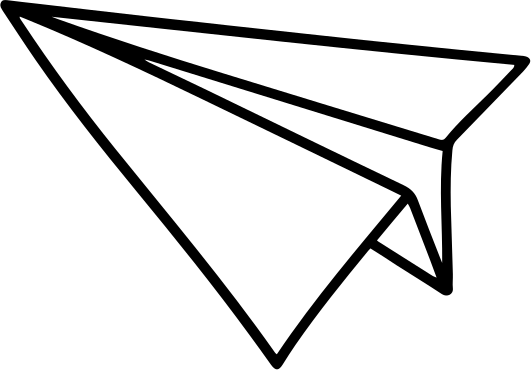 君の誕生日に渡しそびれたプレゼントは机の奥にしまったまま季節が1つ進んで包装紙の角が少し潰れている。君の隣で笑う誰かを見る度に、これを渡すタイミングはもう来ないんじゃないか、いっそ捨ててしまおうと考え、結局毎朝ちゃんとリボンを結び直し引き出しを閉める。何故か鍵はかけていなかった。
君の誕生日に渡しそびれたプレゼントは机の奥にしまったまま季節が1つ進んで包装紙の角が少し潰れている。君の隣で笑う誰かを見る度に、これを渡すタイミングはもう来ないんじゃないか、いっそ捨ててしまおうと考え、結局毎朝ちゃんとリボンを結び直し引き出しを閉める。何故か鍵はかけていなかった。
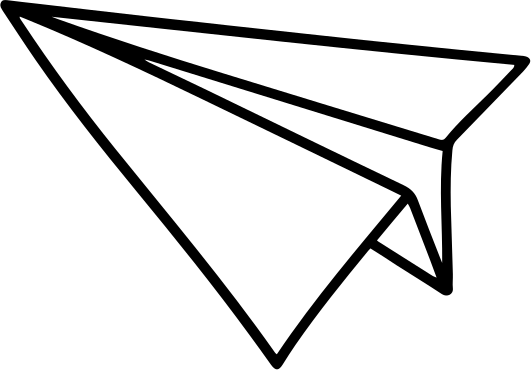 お前の特別を差し出すのが俺じゃない事くらい分かっていた。顔に出すほど子供じゃねえと思ってたが、いざ誰かの名前が口から出た瞬間に笑ったつもりの顔が思いっきり歪んでたらしい。皮肉にもお前が一番に気づいて「かっちゃん」と俺を不思議そうに呼んだ時、腹の奥がじくじくと疼いて吐きそうだった。
お前の特別を差し出すのが俺じゃない事くらい分かっていた。顔に出すほど子供じゃねえと思ってたが、いざ誰かの名前が口から出た瞬間に笑ったつもりの顔が思いっきり歪んでたらしい。皮肉にもお前が一番に気づいて「かっちゃん」と俺を不思議そうに呼んだ時、腹の奥がじくじくと疼いて吐きそうだった。
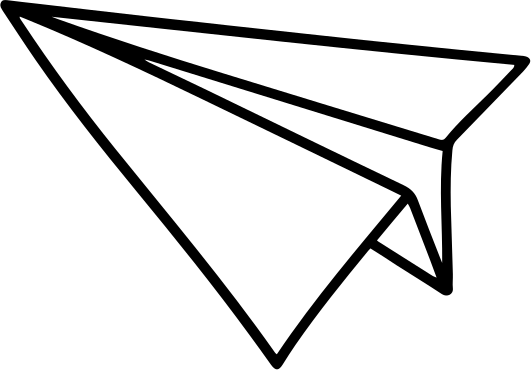 風呂上がり麦茶を一気に飲む君の喉仏が白い喉を上下してるのを、僕はなんとなく目で追っていた。君は「ぷはっ」と景気良く息を吐き、僕の視線に気付くとこちらにグラスを差し出した。「お前も飲むか」と言われたけどそうじゃなくて、僕は君のことを見てたんだって言う勇気は今日も湧いてこなかった。
風呂上がり麦茶を一気に飲む君の喉仏が白い喉を上下してるのを、僕はなんとなく目で追っていた。君は「ぷはっ」と景気良く息を吐き、僕の視線に気付くとこちらにグラスを差し出した。「お前も飲むか」と言われたけどそうじゃなくて、僕は君のことを見てたんだって言う勇気は今日も湧いてこなかった。
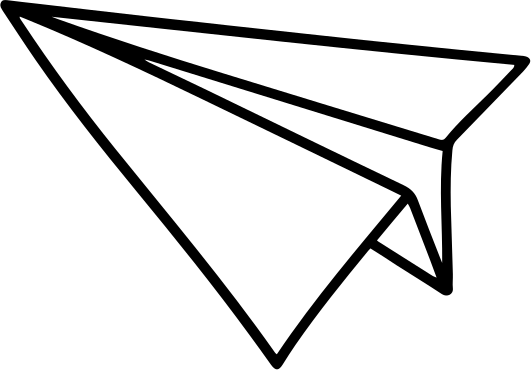 朝の光が差す食卓、俺は出久のカップを無意識に手前へ寄せた。「ありがとう」と言われて初めて気づく。「もしかして寝ぼけてる?」笑う出久の頬にはトーストの欠片。「お前、無自覚で可愛いのやめろ」そう言いながら俺は指でその欠片を払うと「やっぱり寝ぼけてる」と出久は顔を真っ赤にして言った。
朝の光が差す食卓、俺は出久のカップを無意識に手前へ寄せた。「ありがとう」と言われて初めて気づく。「もしかして寝ぼけてる?」笑う出久の頬にはトーストの欠片。「お前、無自覚で可愛いのやめろ」そう言いながら俺は指でその欠片を払うと「やっぱり寝ぼけてる」と出久は顔を真っ赤にして言った。
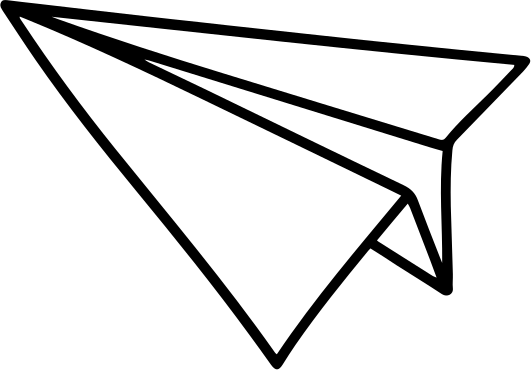 何も無い休日、ソファに座る俺の袖を隣の出久がうとうとしながら引いた。黙って腕を伸ばせば、すぐに俺の肩にもたれかかってきた。寝息が落ち着くまで待って、そっとリモコンに手を伸ばす。……が、届かない。「……おい」返事は無い。諦めて俺も目を閉じると、数分後には健やかな寝息が輪唱を始めた。
何も無い休日、ソファに座る俺の袖を隣の出久がうとうとしながら引いた。黙って腕を伸ばせば、すぐに俺の肩にもたれかかってきた。寝息が落ち着くまで待って、そっとリモコンに手を伸ばす。……が、届かない。「……おい」返事は無い。諦めて俺も目を閉じると、数分後には健やかな寝息が輪唱を始めた。
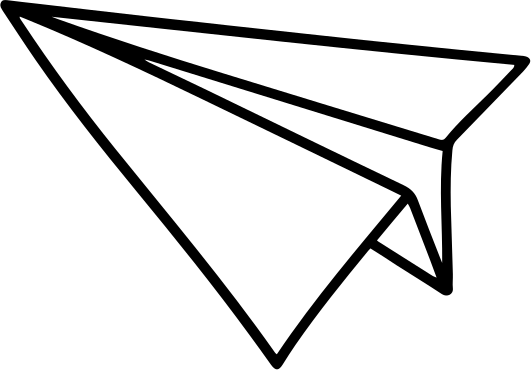 「出久」僕を呼ぶ声が日毎甘くなってくる度僕はつい軽口を叩いた。かっちゃんが綿飴の様な声を霧散させて軽口に応戦する。そうすれば僕らはいつもの幼馴染に戻れた。「怖いか?」かっちゃんが僕に問う。僕は怖いと答えた。綿飴の味を知ってしまった僕が、君無しでいられなくなるのが死ぬほど怖かった。
「出久」僕を呼ぶ声が日毎甘くなってくる度僕はつい軽口を叩いた。かっちゃんが綿飴の様な声を霧散させて軽口に応戦する。そうすれば僕らはいつもの幼馴染に戻れた。「怖いか?」かっちゃんが僕に問う。僕は怖いと答えた。綿飴の味を知ってしまった僕が、君無しでいられなくなるのが死ぬほど怖かった。
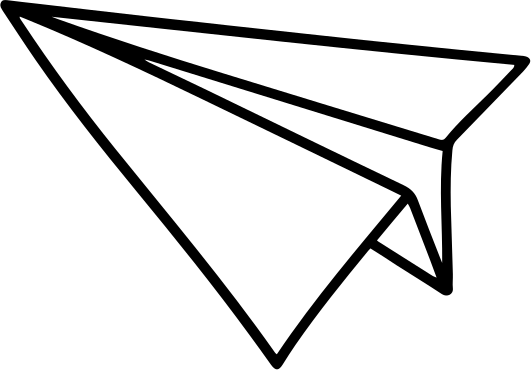 「緑谷先輩とは幼馴染なんですよね」俺は後輩の問いに小さい舌打で返事する。演習中に喋るなと注意も込めた舌打だ。否定も肯定もしない。味がしなくなったガムをずっと噛み続けているように俺は現状に足踏みしていた。「今はな」俺の言葉に後輩は首を傾げた。俺はずっと新しいガムを噛みたがっている。
「緑谷先輩とは幼馴染なんですよね」俺は後輩の問いに小さい舌打で返事する。演習中に喋るなと注意も込めた舌打だ。否定も肯定もしない。味がしなくなったガムをずっと噛み続けているように俺は現状に足踏みしていた。「今はな」俺の言葉に後輩は首を傾げた。俺はずっと新しいガムを噛みたがっている。
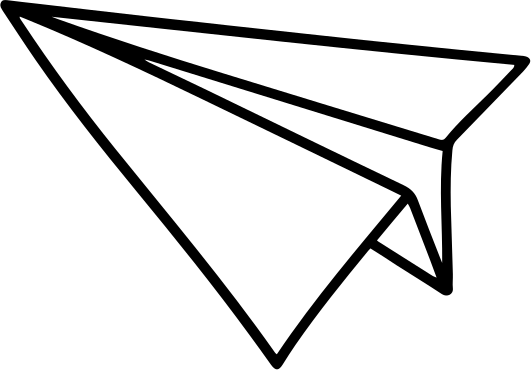 「素直な良い子にはご褒美」怒られるような事でも誤魔化さず素直に話すと、母はそう言って飴玉をくれた。「本当のことを言え」と君は僕の詰襟を絞めた。純粋な憧れなんて疾うに無くなったというのに、君はそれを妄執だと言った。君が好きだなんて誰が言えただろう。言えば飴玉が待っていたのだろうか。
「素直な良い子にはご褒美」怒られるような事でも誤魔化さず素直に話すと、母はそう言って飴玉をくれた。「本当のことを言え」と君は僕の詰襟を絞めた。純粋な憧れなんて疾うに無くなったというのに、君はそれを妄執だと言った。君が好きだなんて誰が言えただろう。言えば飴玉が待っていたのだろうか。
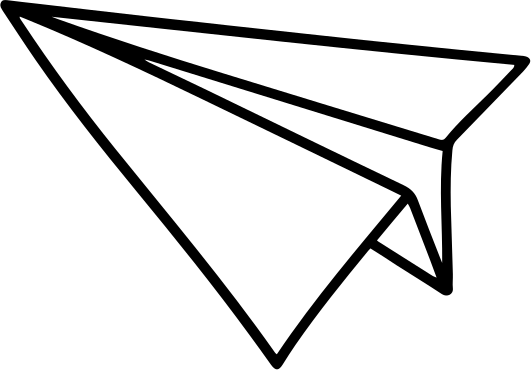 バス停で一緒に待つ女性の手には二つの傘。一つは花柄の傘。もう一つの小さな傘は、見慣れた黒と橙の配色に彼のトレードマークの手榴弾チャームがついている。幼い自分を重ねて僕は自然と笑みを浮かべた。五分後、可愛いファンと一緒にバスから降りてくるヒーローに僕はオールマイトの傘を差し出した。
バス停で一緒に待つ女性の手には二つの傘。一つは花柄の傘。もう一つの小さな傘は、見慣れた黒と橙の配色に彼のトレードマークの手榴弾チャームがついている。幼い自分を重ねて僕は自然と笑みを浮かべた。五分後、可愛いファンと一緒にバスから降りてくるヒーローに僕はオールマイトの傘を差し出した。
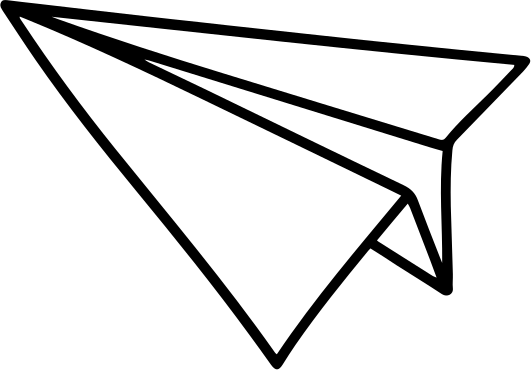 例えばオムライスに使う卵の数、掃除機は紙パック派か、おでんはご飯のおかずになるか。同じ人に憧れた君と僕がこんなに違うのだと突き付けられる。「嫌になったかよ」君の言葉に僕は首を振る。君のデータ更新が捗ると僕が言えば「クソナード」と笑われた。差異を畏れた子供達は、もうどこにもいない。
例えばオムライスに使う卵の数、掃除機は紙パック派か、おでんはご飯のおかずになるか。同じ人に憧れた君と僕がこんなに違うのだと突き付けられる。「嫌になったかよ」君の言葉に僕は首を振る。君のデータ更新が捗ると僕が言えば「クソナード」と笑われた。差異を畏れた子供達は、もうどこにもいない。
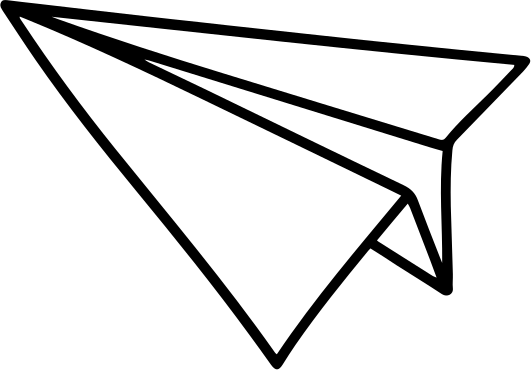 近くに雷が落ちたらしく、飯の準備中に停電しやがった。丁度新月で一寸先も見えやしない。俺が微かに掌を爆ぜると、寝室から出てきた出久がその灯りを見て安心したように「かっちゃん」と近づいてきた。そっからカルガモの親子の様に俺の後をついて来るもんだから、俺は懐中電灯の場所は黙っておいた。
近くに雷が落ちたらしく、飯の準備中に停電しやがった。丁度新月で一寸先も見えやしない。俺が微かに掌を爆ぜると、寝室から出てきた出久がその灯りを見て安心したように「かっちゃん」と近づいてきた。そっからカルガモの親子の様に俺の後をついて来るもんだから、俺は懐中電灯の場所は黙っておいた。
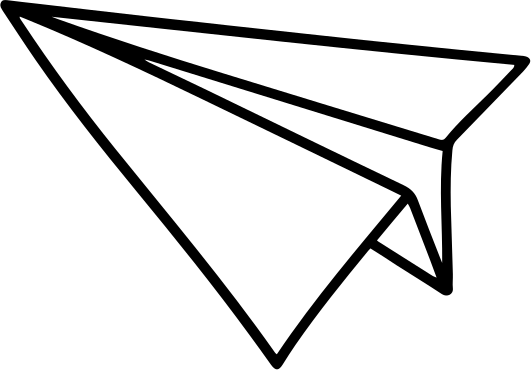 目の前の子供向け歯磨粉に描かれた峰田は、デフォルメされていつものエロ魔人のなりを潜めていた。手慣れた操作で写真と共に「あった」とメッセージを打つと、土下座するオールマイトのスタンプ一つ。いつの間にかフォルダに増えた同じ様な写真を見て苦笑しつつ、俺は歯磨粉を持ってレジに並んだ。
目の前の子供向け歯磨粉に描かれた峰田は、デフォルメされていつものエロ魔人のなりを潜めていた。手慣れた操作で写真と共に「あった」とメッセージを打つと、土下座するオールマイトのスタンプ一つ。いつの間にかフォルダに増えた同じ様な写真を見て苦笑しつつ、俺は歯磨粉を持ってレジに並んだ。
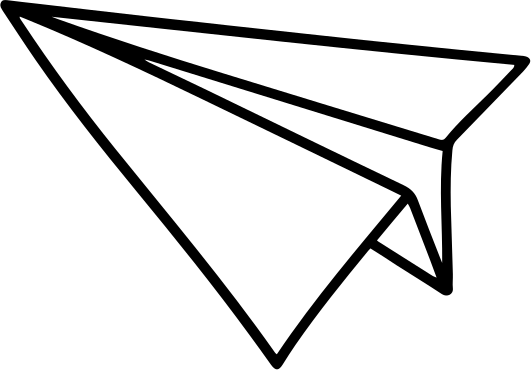 いつもよりドライヤーに時間がかかったから、そろそろ髪切りに行けと言う君に僕は目を丸くした。「今日相澤先生にも言われたよ」僕が驚いたと声に出してそう言うと、かっちゃんは心底悔しそうに舌打ちした。「次は俺が一番に気付いたる」口と目を尖らした顔と裏腹に僕の髪を梳かす指は柔らかかった。
いつもよりドライヤーに時間がかかったから、そろそろ髪切りに行けと言う君に僕は目を丸くした。「今日相澤先生にも言われたよ」僕が驚いたと声に出してそう言うと、かっちゃんは心底悔しそうに舌打ちした。「次は俺が一番に気付いたる」口と目を尖らした顔と裏腹に僕の髪を梳かす指は柔らかかった。
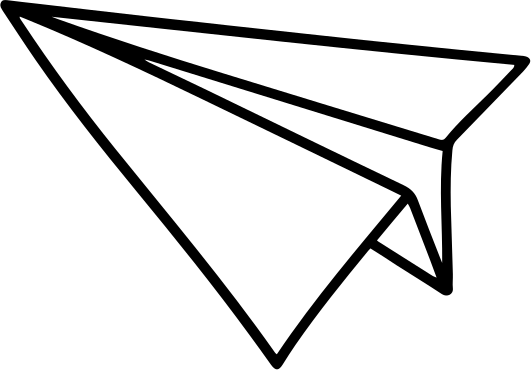 レンジの上にケトルを置いている僕に危ないから置くなと教えてくれた君。知らない事なんてないじゃないかと感心すると、君は一言「お前」と零した。「だから一生かけて研究すんだよ」と悪い顔で言うから研究結果を教えてよと言い返した。「ヨボヨボのジジイになったらな」とまた悪戯っ子の様に笑った。
レンジの上にケトルを置いている僕に危ないから置くなと教えてくれた君。知らない事なんてないじゃないかと感心すると、君は一言「お前」と零した。「だから一生かけて研究すんだよ」と悪い顔で言うから研究結果を教えてよと言い返した。「ヨボヨボのジジイになったらな」とまた悪戯っ子の様に笑った。
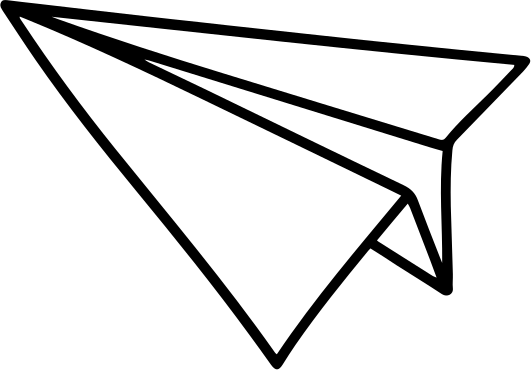 いつまでも慣れない僕の為に、その手を僕に伸ばす度「いいか」って尋ねる君に、僕はいつだって「もちろん」って答える。そろそろ僕だって、と真似して「いいよね」と君の頬に唇を寄せると、君は「ダメだ」と言って僕の顔をその手で覆った。指の隙間から見えたかっちゃんの顔は、赤く色付いていた。
いつまでも慣れない僕の為に、その手を僕に伸ばす度「いいか」って尋ねる君に、僕はいつだって「もちろん」って答える。そろそろ僕だって、と真似して「いいよね」と君の頬に唇を寄せると、君は「ダメだ」と言って僕の顔をその手で覆った。指の隙間から見えたかっちゃんの顔は、赤く色付いていた。
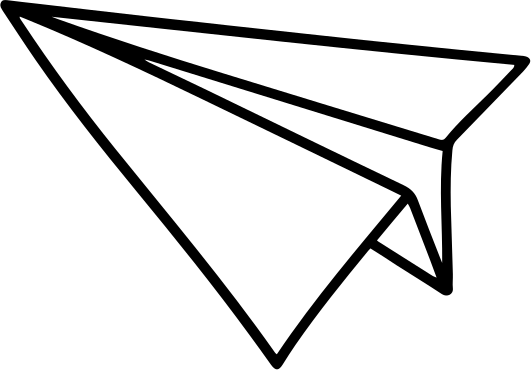 老夫婦がするようなデートをした。季節の花が咲く公園を一日かけて歩くだけ。時折気に入った花を見つけ立ち止まった出久が、トイカメラを向けて安いシャッター音を響かせる。「みて」画面一杯に二つの黒い影と頭の所に菊の花が薄暗く写っていた。「お人形みたい」菊人形は粗い画質の中寄り添っていた。
老夫婦がするようなデートをした。季節の花が咲く公園を一日かけて歩くだけ。時折気に入った花を見つけ立ち止まった出久が、トイカメラを向けて安いシャッター音を響かせる。「みて」画面一杯に二つの黒い影と頭の所に菊の花が薄暗く写っていた。「お人形みたい」菊人形は粗い画質の中寄り添っていた。